PROJECT STORY 01
CHALLENGE
三菱地所から、スタートアップ
新事業提案制度
若い発想から生まれる新会社は、
三菱地所にどんな化学反応を
起こすのか?
 RECRUITING SITE
RECRUITING SITE
PROJECT STORY 01
CHALLENGE
三菱地所から、スタートアップ
若い発想から生まれる新会社は、
三菱地所にどんな化学反応を
起こすのか?

佐々木 謙一
Hmlet Japan株式会社
代表取締役 兼 住宅業務企画部 主事
経済学部 経済学科 卒
2006年入社

加川 洋平
GYYM株式会社
代表取締役 兼 新事業創造部 主事
創造理工学研究科
経営システム工学専攻 修了
2011年入社

橋本 龍也
GYYM株式会社
代表取締役 兼 新事業創造部 副主事
経済学部 経済学科 卒
2011年入社
※所属、掲載内容は取材当時のものです


橋本
佐々木さんが代表取締役を務める『Hmlet Japan(ハムレット・ジャパン)』も、私と加川が共同代表の『GYYM(ジーム)』も、三菱地所の新事業提案制度によって設立されたスタートアップ企業ですね。
佐々木
そうですね。どちらも同じ時期、2018年に提案した事業プランから誕生した会社ですね。 『Hmlet Japan』は、Co-Living事業を日本で展開する会社で、三菱地所と東南アジア最大のCo-Living運営会社であるHmlet社との合弁のもとに設立しています。日本の住宅ビジネスはシンプルで、「駅からの距離」と「築年数」によって、ほぼその価値が決まります。そうではなく、『Hmlet Japan』では、入居者にコミュニティを提供しつつ、デジタル技術を活用して安価に様々なサービスを提供するなど、住まいに新しい価値を付加しています。 また、家具・家電付きの部屋を用意し、敷金・礼金といった転居の際に発生するイニシャルコストも大幅に抑えるなど、フレキシブルなライフスタイルをサポートしていることも大きな特徴ですね。
加川
私たちの『GYYM』では、多種多様なフィットネスクラブやジムなどを個別の入会金を支払うことなく、「好きな時に好きなだけ」利用できる「1 TICKET FITNESS(都度利用制度)」を提供するプラットフォームの運営を行っています。 利用者は、月会費などを気にすることなく自分にあったフィットネス施設を手軽に予約・利用でき、フィットネス施設にとっては収益性の向上や新規会員獲得機会の増加というメリットが見込めます。
佐々木
『GYYM』は、加川さんと橋本さんが共同の代表者になっていますが、そのきっかけがユニークでしたよね。
橋本
そうなんです。そもそもは新事業提案制度の社内セミナーの場で偶然にも同期の4人が顔を揃えたことがスタートでした。そのセミナーで、「ごく身近な問題から課題を見出してビジネスにつなげよう」という話を聞いて、それをきっかけに4人でミーティングを重ね、『GYYM』の原型となるアイデアが生まれました。
加川
正直言うと、セミナーに参加した時点では、「新しい事業を起こしたい」という意欲はあったのですが、誰も具体的なプランは持っていませんでした(笑)。 佐々木さんは、どういうきっかけで起業を思い立ったのですか?
佐々木
私は当時シンガポールに駐在していて、東南アジアの不動産デベロッパーと合弁会社を組成し、日本のノウハウを提供しつつ、東南アジアで不動産開発プロジェクトを担当していました。その業務の傍ら、海外駐在というせっかくのチャンスを活かして、現地のスタートアップや不動産テック分野の人たちにコンタクトして、自分なりに現地の情報を収集していたのです。『Hmlet』は、そのような活動を通じて、知り合った会社の一社でしたが、日本においても可能性のある事業だと思いました。

橋本
2018年夏に、私たちが応募した新事業提案制度の第1次審査が行われ、20組程度が応募して、私たちを含め6件が一次審査を通過しました。そこからが本番。ハードな日々の連続でしたね(苦笑)。
加川
1次審査を通過すると、自分がいる部署と新事業創造部の兼務という形になり、2週間に1回のペースで起業に向けたメンタリングが行われました。ちょうど私たちと佐々木さんは同じメンターの方から学ぶことになりましたよね。インキュベーターとしても経験豊富なとても優秀な方がメンターとして指導してくれるのですが、それが厳しくて……(笑)。
佐々木
でも、毎回新しい発見の連続で、もの凄く刺激的でしたよね。
橋本
ボトムアップのアプローチ、つまりユーザーへのヒアリングをとにかく大事にすることがとても新鮮でした。自分の友人やその友人、同期や先輩など、自分に近い人たちを起点にヒアリングを行いました。
加川
本来の業務もしながら、わずかな期間に何十人ものインタビューをしました。自分たちが立てた仮説を徹底的に検証するわけです。あの時期は本当に大変だった(笑)。
佐々木
「ニーズのメカニズムを特定しなさい」というものですよね。それをロジカルに言葉できちんと説明できないといけない。少しでも曖昧だと、すぐに指摘されてしまう。
橋本
そんな検証を積み重ねながらビジネスモデルを少しずつ形にし、その年の秋に行われた第2次審査もお互いに無事に通過。翌2019年の春には厳しかったメンタリングもようやく“卒業”して、そこから起業に向けての動きがいよいよ加速しましたね。

佐々木
私の場合、シンガポールにあるハムレット社と合弁に向けた交渉を進めていたので、すでにその前段階から本格化していた感じですね。
加川
『GYYM』ではその後、ヒアリングで顕在化してきたターゲット層向けに仮想サービスをつくり、実際にユーザーを募ってオフラインで実証テストを行い、事業化に向けての確証データを積み上げていきました。
橋本
そんなステップを経て、新会社を設立し、『GYYM』のビジネスをプレローンチしたのは2020年の1月ですね。



佐々木
『Hmlet Japan』の事業がスタートしたのは、『GYYM』より少し早い2019年10月。渋谷の松濤に第1号物件を開業しました。その後、2020年3月に笹塚でも開業し、今夏、さらに都内で5物件を開業しました。
加川
事業をスタートして早々にコロナ禍という想定外の事態に直面しましたが、影響はどうでしたか?
佐々木
正直なところ、それなりにありますね。『Hmlet Japan』では、外資系企業の駐在員を一つのターゲット層にしていたのです。しかし、その層が縮小してしまったので戦略を転換しました。それでもビジネスとしては比較的順調だと思います。2020年度中に東京都心で300室以上、また大阪での展開を進めるつもりで準備を進めています。
加川
それは素晴らしいスタートですね。
橋本
『GYYM』では2カ月間のプレローンチを経て2020年4月にサービスをスタートする計画でした。ところが、コロナ禍によって中断し、6月に再開したところです。コロナ禍は想定外の事態ですが、『GYYM』のコンテンツで早くも注目を集めているフィットネス施設があります。そのような成功例を切り口に、ポストコロナに向けてニーズのメカニズムを再検証している最中です。
加川
いまは、オンラインフィットネスといったコロナ禍によって生まれてきた新しいニーズもコンテンツに取り込んでいます。
ところで佐々木さんは、起業家として、いまどのあたりに一番気を配っていますか?
佐々木
チームとしてのモチベーションをいかに高めていくかということでしょうか。現在、『Hmlet Japan』の社員は12名。うち3分の1が外国人です。
加川
『GYYM』の場合、システム開発とデジタルマーケティングのチームで構成されますが、社員ではなく全メンバーが業務委託というスタイルです。それでもメンバーのモチベーションアップは非常に大切ですね。
佐々木
起業家としての面白さはどう感じていますか?
橋本
やはり自分たちで意思決定をできるということが一番大きいと思います。逆に誰のせいにもできないという苦しさもありますが、もの凄く貴重な経験を積んでいる実感があります。
加川
私も同感です。方向性が8割くらい見通せるような案件ならまだしも、時には成否が五分五分くらいの状況で腹をくくって決断しなければならないこともある。この経験は、いままでの世界観とはぜんぜん違います。 もっとも私たちは共同経営者として二人で決断するので、一人である佐々木さんよりもプレッシャーは若干少ないかもしれませんね(笑)。
佐々木
それは最初のメンタリングの時からずっとうらやましいと思っていました(笑)。ですが、『Hmlet Japan』のなかには、同じ目線で事業を推進してくれる仲間がいるので、実際はそれほどプレッシャーが強いわけではありません。

橋本
佐々木さん、三菱地所で社内起業する魅力として、どんなところがあげられると思いますか?
佐々木
一般的なスタートアップと比べると、様々な意味で環境がとても恵まれていますよね。さきほど話をしたメンタリングのように、起業を支援してくれる環境も非常に充実しています。
加川
私と橋本がそうだったように、新事業を見出す段階からサポートしてくれることも恵まれた環境の一つだと思いますね。
橋本
私が一番に感じるのは、三菱地所グループならではの資産をフルに活用できること。なかでも不動産というリアルな事業を通じて蓄積してきた膨大な顧客ネットワークは、一般のスタートアップでは絶対にリーチできない資産だと思います。
加川
気の早い話ですが、いまスタートアップとして経験していることを三菱地所でどのように生かしていきたいと考えていますか?
佐々木
いまは目の前にある事業に集中していて将来のことまで目線がいかないのですが、一つ感じているのは、いま私たちがベンチャー界隈に身を置いて実感しているビジネスのスピード感、その現場で学んでいるデジタルマーケティングやDXなどの技術は、これからの三菱地所にとって絶対に必要となる要素だということですね。
加川
私もそれは実感しています。いま私たちが蓄積している知見と、三菱地所の事業やアセットを掛け合わせることによって、将来さらに新しい事業を生み出せるはずです。
橋本
同感です。私は、そもそもまちづくりに携わりたいという想いから三菱地所に入社しました。その気持ちは現在も変わりませんが、いま自分たちで起こした新規事業を成功に導くことが、その先の将来に繋がると思い、懸命に取り組んでいます。
※所属、掲載内容は取材当時のものです

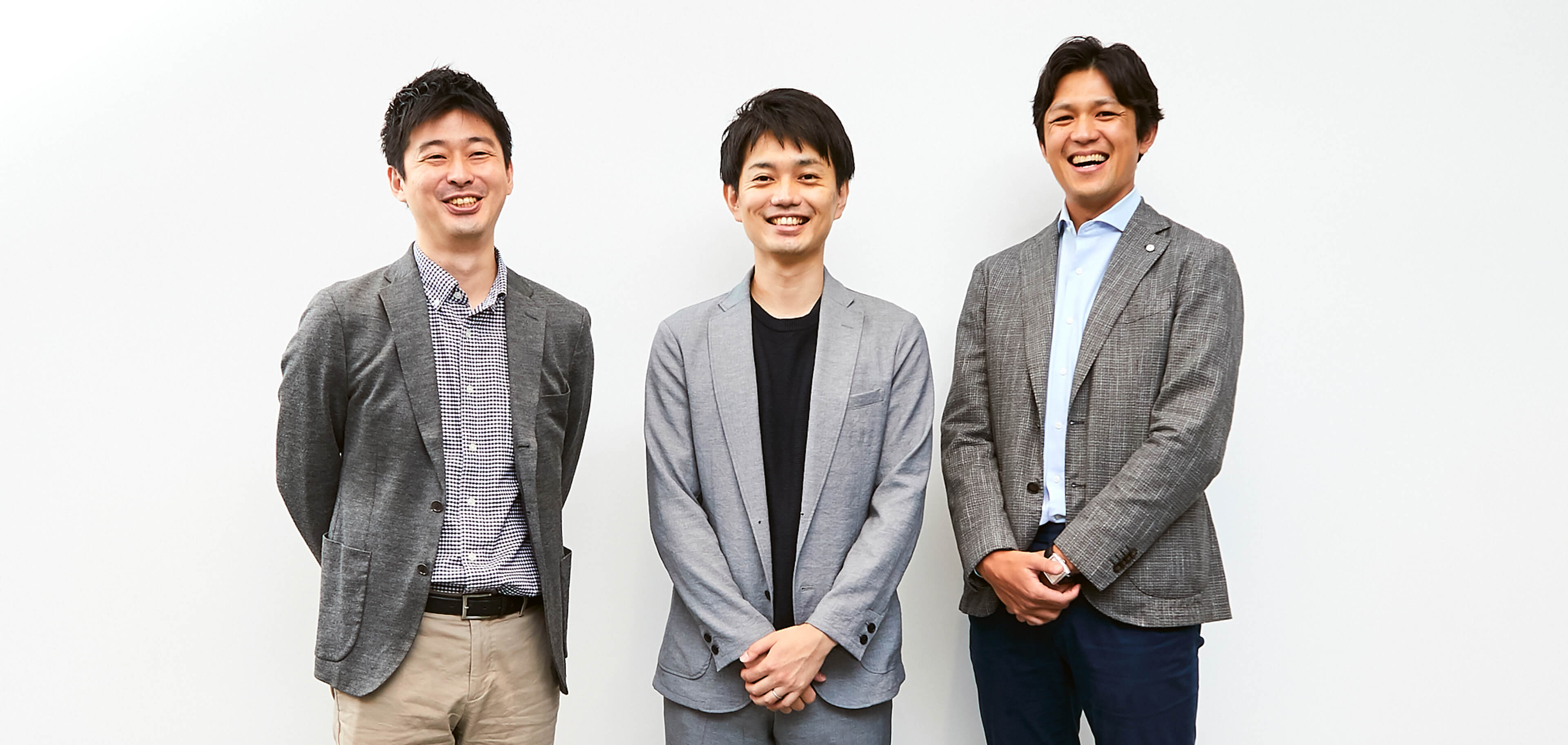
 PROJECT STORY
新事業提案制度 | 三菱地所からスタートアップ
PROJECT STORY
新事業提案制度 | 三菱地所からスタートアップ
 PROJECT STORY
TOKYO TORCH | 日本を明るく、元気にする
PROJECT STORY
TOKYO TORCH | 日本を明るく、元気にする
 PROJECT STORY
大丸有エリア開発 | 東京を、日本を先導するまちづくり
PROJECT STORY
大丸有エリア開発 | 東京を、日本を先導するまちづくり
 PROJECT STORY
横浜エリア開発 | みなとみらいから、つながる、ひろがる
PROJECT STORY
横浜エリア開発 | みなとみらいから、つながる、ひろがる
 PROJECT STORY
グラングリーン大阪 | みどりとイノベーションの融合
PROJECT STORY
グラングリーン大阪 | みどりとイノベーションの融合
 PROJECT STORY
泉パークタウン開発 | 民間で日本最大級のニュータウン開発
PROJECT STORY
泉パークタウン開発 | 民間で日本最大級のニュータウン開発
 PROJECT STORY
In Australia| | CHALLENGE IN AUSTRALIA
PROJECT STORY
In Australia| | CHALLENGE IN AUSTRALIA
 PROJECT STORY
In HO CHI MINH CITY | 大いなるポテンシャルを秘めたベトナム
PROJECT STORY
In HO CHI MINH CITY | 大いなるポテンシャルを秘めたベトナム